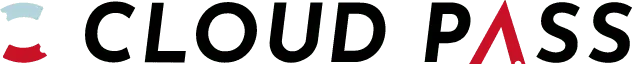クラパス活用術
チケットもぎりとは?注意すべきポイントも解説
更新日:
投稿日:
イベントやコンサート会場の入り口で来場者のチケットを確認し、入場させる役割を担うのがチケットもぎりです。
チケットもぎりは一見すると単純作業のように見えますが、スムーズな入場誘導や不正入場防止など、イベントの成功を左右する重要な役割を担っています。
この記事では、チケットもぎりの詳細や業務の流れ、注意点などを詳しく解説します。イベントを成功させるためにも、役割の重要性を正しく理解することが大切です。
チケットもぎりの業務内容に興味のある方や、スムーズなイベント運営を実現したい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
チケットもぎりとは
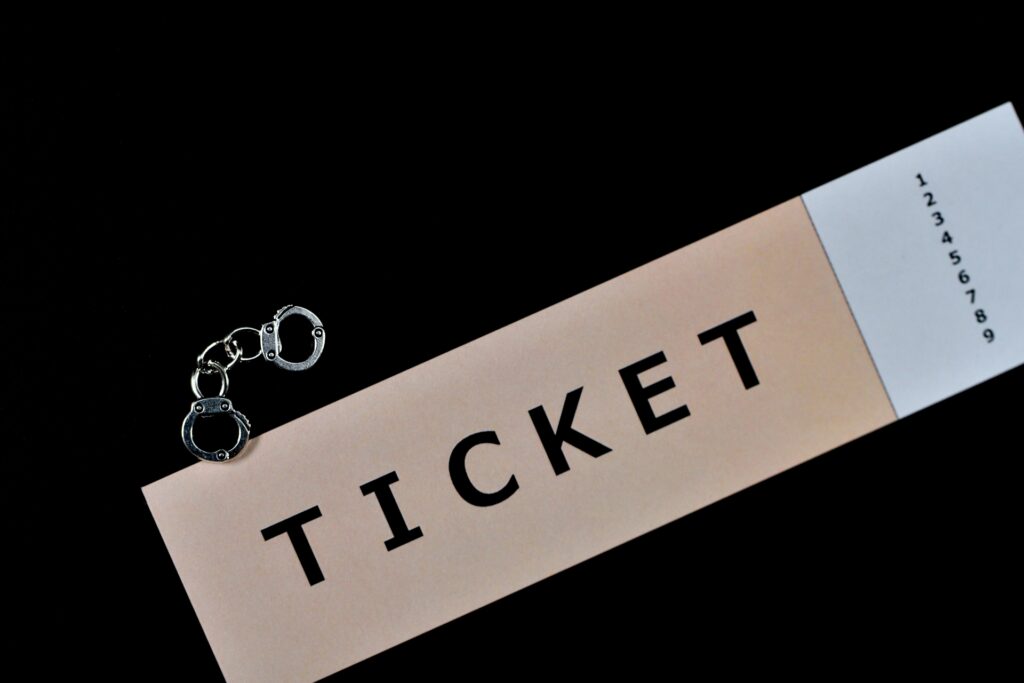
チケットもぎりとは、イベントやコンサート会場の入り口で、来場者が持っているチケットを確認し、入場させる業務やそのスタッフのことです。チケットに記載された内容を確認し、不正な入場でないかチェックします。
チケットもぎりは、チケットを「もぎ取る」という言葉が由来です。一部をもぎ取って半券をお返しすることで、そのチケットが使用済みであることを示します。
ただ確認するだけの作業と思われがちですが、安全面への配慮や接客のスキルも求められるなど、イベント運営において重要な業務です。
チケットもぎりの役割
チケットもぎりのおもな役割は、入場者から提示されたチケットの記載内容(日時、会場、座席番号など)に誤りがないか確認することです。まれに日時や会場を間違えて来場する方がいるため、有効なチケットでない場合はその旨の説明をしてお帰りいただくことになります。
中には日にちを間違えて入場できないことを知り、ショックで立ち止まってしまう人もいます。そのような場合、後の列に影響が出ることもあるため、迅速な対応が必要です。ただし、スタッフが思いやりのない対応をしてしまうと、クレームや悪評につながるおそれもあります。
また、チケットもぎりスタッフには混雑状況を把握し、安全な入場管理を行うことも求められます。滞りがないようにイベントを進行していくためにも、正確かつスピーディに仕事をこなし、丁寧な案内を実施しなければなりません。
そして、悪意を持って来場する人はそう多くはありませんが、不正入場を防ぐこともチケットもぎりの目的の1つです。偽造や不正による入場を防止するためにも、チケットの内容を正しく確認することが求められます。
チケットもぎりの重要性
チケットもぎりと聞くと、流れ作業のような業務をイメージする方もいるかもしれません。しかし、チケットもぎりはイベントの円滑な運営を支える上で重要な役割を担っています。
まず、イベントの第一印象を左右する点があげられます。チケットもぎりのスタッフは、来場者が最初に接する存在です。スムーズな対応ができれば、来場者はよい印象を維持しながら来場でき、イベントへの期待感も高まります。反対に、もたつきや不愛想な対応があると、来場者は不快な思いをし、イベント全体の印象を悪くするおそれがあるでしょう。
また、不正入場を防止することはもちろん、会場内の安全管理も業務の一環です。具体的には混雑状況を把握し、必要に応じて誘導や整理を行いながら、事故や混乱を未然に防いでいます。
多くの来場者にとって、チケットもぎりスタッフの存在はあまり意識されないかもしれません。しかし、その業務が滞りなく行われることで、イベント全体の流れがスムーズになり、来場者は快適に楽しめるのです。
チケットもぎり一日の流れ

チケットもぎりの業務の流れは、イベントの規模や会場、システムなどによって異なりますが、一般的なイベント会場における1日の業務の流れを下記に示しました。
| 業務 (時間) | 内容 |
| 準備(8:00~) | 担当場所の確認:担当する入り口や場所を確認する 資料の準備:チケットと照らし合わせるリストや資料(座席表など)を用意する 配布物の準備:案内図やパンフレットなどの配布物があれば準備する スタッフ間での打ち合わせ:当日の流れや対応についてすり合わせを行う |
| 業務開始(9:00~) | 来場者の誘導:来場者がスムーズに入場できるよう列を整理する 来場者のチケットを確認:チケットに記載された内容(日時、会場、座席番号など)と来場者を照合する チケットをもぎる:チケットの一部をもぎ取って半券をお返しする(電子チケットの場合は来場者に手順を案内) 会場内への案内:会場内へスムーズに誘導する チケット半券の管理:回収したチケットの半券を整理し、管理する 参加者の見送り:イベント終了後、ゲート付近の安全確認を行いながら参加者の退場を見送る |
| 業務終了(17:00) | 備品の片づけ:使用した備品の片づけを行う 報告書の作成:当日不備やトラブルがなかったか確認し、必要に応じて当日の状況や問題点などを報告する |
チケットもぎりは1日立ちっぱなしであることも多く、集中力が求められる業務です。なお、イベントスタッフとして携わる場合は、チケットもぎりだけでなく会場の設営や撤収を任せられることもあります。当日は状況を見ながら、臨機応変に対応することが大切です。
電子チケットの普及がもたらすチケットもぎり
電子チケットとは、従来紙製だったチケットをデジタルデータ化したものです。オンラインチケットやeチケットなど、さまざまな呼称があります。電子チケットは、スマートフォンやインターネットの普及や消費者ニーズの変化、技術の進歩などの要因により、一般的に利用されるようになりました。
電子チケットの特徴は、申し込みや決済、入場までスマホ1台で完結できることです。利用者にとって利便性がよく、イベント主催者やチケットもぎりスタッフにとってもさまざまなメリットがあります。
ここからは、電子チケットの導入によって得られるメリットを下記3つの観点で解説します。
・業務効率の向上
・セキュリティの向上
・時間短縮
それぞれ確認していきましょう。
関連記事:電子チケットとは?具体的な使い方や導入のメリット・デメリットを紹介
業務効率の向上
従来の紙チケットでは、スタッフが1枚ずつ目視でチェックして、内容に間違いないか逐一確認する必要がありました。一方、電子チケットではQRコードやバーコードによる認証ができ、効率よく案内できる点がメリットです。
立ち作業でチケットを目視する作業は疲労を感じやすいですが、電子チケットであれば機械がチェックするため、スタッフの負担を軽減できます。さらに、目視によるヒューマンエラーの防止につながる点でも優れています。
また、紙チケットを販売する際は、販売業務に対応するスタッフの配置が常に必要です。電子チケットであれば時間や場所を問わず、いつでもチケットを販売できるため、人的コスト削減にも役立つでしょう。
セキュリティの向上
電子チケットは紙製のチケットに比べて偽造や不正入場が難しく、セキュリティ上のリスクを大幅に軽減できるメリットがあります。電子チケットはQRコードやバーコードなど固有の識別情報を持つため、複製や改ざんが困難です。
さらに電子チケットのセキュリティには、IDやパスワードによる本人確認、暗号通信、不正ログイン防止などの仕組みがあります。昨今ではチケットの転売も大きな問題となっていますが、電子チケットであれば購入者の個人情報と紐付けられるため、譲渡や転売の制限が可能です。
時間短縮
電子チケットを使った入場手続きは、QRコードやバーコードなどから情報を読み取るだけです。紙チケットのように、係員が1枚ずつ確認したり、半券をもぎったりする必要がありません。入場ゲートでの待ち時間を大幅に短縮し、スムーズな入場を実現できます。
会場入り口での当日券販売も、電子チケットであれば簡単に手続きが可能です。現金でのやり取りや、紙チケットの発券作業が不要になるため、当日券購入者の待ち時間短縮につながるでしょう。
また、電子チケットは、リアルタイムでチケット販売状況や入場者数を把握できる点でも優れています。チケットの売れ行きをスムーズに把握できるため、イベント運営を円滑に進められます。
チケットもぎりは自動化できる?
近年、電子チケットの普及により、チケットもぎりの自動化が進んでいます。これまでは、電子チケットを導入しても、スタッフがQRコードの表示方法や手順を案内する必要がありました。
最新の技術では、駅の改札機のようにチケット情報を読み取って自動で入場を許可する「自動改札機型」のシステムを導入するイベントも注目されています。チケットの読み取り方法については、スマホを通じた案内や、ゲート付近への掲示といった工夫により、スタッフの手間を軽減する試みも実践されてきました。
また、顔認証システムとチケット情報を連携させることで、より高度な自動化も実現可能です。顔認証システムを導入した電子チケットであれば、事前に顔情報を登録しておくことで、チケットの提示なしで入場できるようになります。
チケットもぎりの自動化は、本人確認作業を効率化できるだけではく、チケットの不正利用防止の観点でも有効です。ただし、自動化にはさまざまな種類のシステムがあるため、イベントの特性や利用者層などを踏まえて、より効果的なものを導入する必要があるでしょう。導入後も効果測定を実施し、施策と改善を重ねていくことが求められます。
関連記事:【2025年最新】QRコード受付システム・アプリおすすめ10選!失敗しない選び方も解説
もぎりの正しい手順
一般的なチケットもぎりの正しい手順は、それぞれ以下のとおりです。
【紙チケットの場合】
1.確認:チケットの日時、会場、座席番号などを確認する
2.もぎり:指定箇所を切り取り、半券を回収する(点線などに沿って折り目をつけてから切り取るとスムーズ)
3.誘導:座席や入場口を案内する
【電子チケットの場合】
1.確認:QRコードやバーコードを読み取り、チケット情報を確認する
2.認証:問題がなければ自動的に入場が許可される
3.誘導:座席や入場口を案内する
どちらのチケットの場合であっても、丁寧かつ迅速、正確な対応が求められます。チケットもぎり担当のスタッフは安全管理を行うため、入場ゲート付近の混雑状況を常に把握し、列の整理にも気を配らなければなりません。
また、万が一事故やトラブルが発生した場合に備えて、緊急時の対応手順や役割分担などについて定めたマニュアルをスタッフ全員で共有し、理解しておくことが大切です。
イベントによっては、当日限りのメンバーである場合も少なくありません。スタッフ間の連携体制を整えておくためにも、最低限の挨拶や会話で交流を図るとよいでしょう。
もぎり時に注意すべきポイント

チケットもぎりはイベント運営において、重要な役割を担っています。来場者全員がスムーズかつ安全にイベントを楽しめるよう、以下の注意点を押さえておきましょう。
・不正、偽造チケットがないか
・チケットの種類は正しいか
・特別なサポートを要していないか
・周囲の安全は確保されているか
それぞれ解説します。
不正・偽造チケットがないか
不正入場や偽造チケットなどに注意することは、イベントの収益を守るだけでなく、来場者同士のトラブルを避けるためにも大切です。
印刷が粗雑なチケットや、ホログラムや透かしなどの偽造防止対策がないチケットは、不正・偽造の疑いがあります。また、チケットの券面が汚れていたり、破れていたりする場合も、注意が必要です。
具体的には、チケットを光に透かして見たり、角度を変えてみたりすることで、偽造の痕跡を見つけやすくなります。また、ブラックライトや拡大鏡などを用いることで、より詳細な確認が可能です。
不正・偽造の疑いのあるチケットを見つけた場合の一般的な対応として、その場で来場者に事情と、確認の時間をいただく旨を伝える流れになります。その際も、不正チケットと決めつけて高圧的な態度になることのないよう、あくまで丁寧な言葉遣いで対応することが大切です。
チケットの種類は正しいか
イベントによっては、一般チケットや招待チケット、割引チケットなど複数の種類のチケットが存在します。チケットもぎりのスタッフは種類を確認し、来場者を正しく案内しなければなりません。
チケットの種類ごとに利用条件は異なり、招待チケットは特定の人物のみが使用できる、割引チケットは特定の条件を満たす人のみが使用できるといった形になっています。チケットによっては年齢制限が指定されていることもあり、チケットの種類を誤ると、大きな問題に発展しかねません。
来場者が提示したチケットの種類に誤りがあった際、適切に対応するためにも、スタッフは各種チケットの種類や特徴を把握しておく必要があります。種類を確認する際は、チケットに記載された番号やチケットの色、デザインなどを確認して識別しましょう。なお、電子チケットの場合は、機械が読み取った内容に沿って案内することになります。
もし、チケットの種類が間違っている場合は、来場者に事情を説明しなければなりません。この場合も丁寧な言葉遣いで対応し、混乱を招かないように注意しましょう。
特別なサポートを要していないか
イベントによっては、特別なサポートを必要とする来場者が訪れることもあります。たとえば、車椅子利用者や介助犬同伴者などが来場した場合は、サポートや特別な配慮が必要です。
車椅子利用者には動線にスロープを設置する、介助犬同伴者には同伴者用のスペースへ案内するなど、速やかにスタッフに連携し、適切なサポートを提供できるように手配しましょう。
また、サポートや配慮を必要とする来場者が訪れる場合は、必要な対応について事前にスタッフ間で共有しておくことが大切です。設備を整えることはもちろん、スタッフそれぞれが状況を理解し、臨機応変に対応できるように連携体制を築きましょう。
周囲の安全は確保されているか
来場者はもちろん、スタッフ自身の安全を守るためにも、周囲の安全に気を配る必要があります。たとえば、以下のような点に注意しましょう。
・通路は十分な幅が確保されているか
・段差や障害物はないか
・不審な人物や物がないか
・来場者がスムーズに移動できるか
転倒や事故のリスクはないか
混雑時には、必要に応じて誘導スタッフの配置や通行規制などの対策が求められます。
入場ゲート付近が混雑している場合は、列の整理や誘導を行いながら、不審な人物がいないか、周囲に気を配るようにしましょう。もし、不審な人物や物を見つけた場合は、速やかに責任者へ報告し、指示にしたがって対応します。
また、緊急時の避難経路や誘導方法を事前に確認しておき、いざという時に対応できるようにしておくことも大切です。楽しいイベントを実現するためにも、安全確保に努めてください。
もぎり業務のトラブル対応
チケットもぎり業務では、しばしばトラブルに遭遇するケースがあります。もぎりスタッフは来場者との最初の接点であるため、対応によってはイベント全体にも影響しかねません。
トラブル発生時は初動が大切です。基本的な対応は、相手の主張や要望を正しく聞くこと、トラブルとなる要因を把握することが求められます。
クレーム対応では、不満を抱えた来場者の気持ちを和らげて、トラブルの拡大を防がなければなりません。ただし、事実関係が不明瞭な段階で謝罪すると、却ってトラブルをこじれさせてしまう要因になります。
トラブルが起きたときは、正しく相手の気持ちや状況を理解し、要望に対してできることだけを示すようにしましょう。具体的には、以下の点を心がけて対応します。
・お客様の安全を優先して考える
・スタッフは冷静さを保って応対する
・相手の気持ちに寄り添い、理解を示す
・状況を把握し、適切な処置を行う
・確約できないことは言わない
クレームが発生した際、その場にいるスタッフの勝手な判断で対応すると、問題がさらに大きくなるおそれもあります。マニュアルが共有されている場合は、トラブル対応手順に沿って対応しましょう。マニュアルにない事態が発生したときは、対応したスタッフだけで判断せず、責任者に指示を仰ぐことが大切です。
トラブルを未然に防ぐ方法

トラブル発生時の対応を決めておくことも大切ですが、あらかじめ予防しておくことで、安心安全なイベント運営につながります。トラブルの発生や拡大を防ぐためには、以下のポイントを押さえておくことが大切です。
・スタッフ間で情報を共有する
・シミュレーションを行う
・参加者に情報提供する
それぞれ確認していきましょう。
スタッフ間で情報を共有する
トラブルを避けるには、イベントに関わるすべてのスタッフが、イベントの内容や必要な対応について把握しておくことが大切です。具体的には、以下のような情報を共有しておきましょう。
・イベントの目的や内容
・イベントのタイムテーブル
・各スタッフの役割分担と責任範囲
・緊急時の避難経路
・緊急時の連絡先
・過去のトラブル事例とその対策
・お客様からのよくある質問
・クレームが起きたときの対応
これらの情報を共有する方法としては、ミーティングやブリーフィング、マニュアル作成などがあげられます。とくに、イベント開始前には必ずミーティングを行い、スタッフ全員が情報を共有し、共通認識を持つことが重要です。
また、イベント期間中も、定期的な情報交換や進捗状況の共有を心がけることで、予期せぬ事態にも対応しやすくなります。たとえば、お客様からの問い合わせ内容や、現場で発生した小さなトラブルなどを共有することで、大きなトラブルに発展する前に対応しやすくなるでしょう。
シミュレーションを行う
シミュレーションは、起こりうるトラブルを事前に予測し、対策を立てる上で有効な手段です。スタッフ間でシミュレーションを実施することにより、実際にトラブルが起きた場面での対応について認識が深まるだけでなく、問題点や改善点の洗い出しにつながります。
具体的には、以下のような状況を想定するとよいでしょう。
・来場者のチケットに誤りがあるとき
・来場者がチケットを忘れたとき
・不正チケットでの入場が疑われるとき
・お客様同士のトラブルが発生したとき
・機器のトラブルが発生したとき
・緊急事態(事故、災害など)が発生したとき
参加者に情報提供する
参加者がイベントの内容や注意事項を事前に把握できる仕組みにしておくと、無用なトラブルを避けることにつながります。具体的には、以下のような情報を参加者に提供するとよいでしょう。
・イベントの内容
・タイムテーブル
・会場へのアクセス方法
・来場時の受付の流れ
・持ち物や服装
・注意事項や禁止事項
・避難経路
必要な情報はSNSやメール、Webサイト、パンフレットなどのさまざまな手段を通じて発信することで、より多くの参加者に情報を届けられます。
また当日も、イベント内容の掲示や、スタッフによる注意事項の案内を行うことが大切です。多くの参加者に情報を届けられるように工夫することで、トラブルを避けられるだけでなく、来場者が安心してイベントを楽しめるようになります。
もぎり業務中の緊急対応とは?
イベント中に起こりうる緊急事態は、地震や火災などの自然災害、不審者の侵入、参加者の体調不良、事故などさまざまな事態が想定されます。
これらの緊急事態に対し、適切な対応を行うためには事前準備が不可欠です。まず、リスクアセスメントを行い、どのような緊急事態が起こりうるかを洗い出します。そのうえで、それぞれの事態に対応するための具体的な対策を立てることになります。
たとえば、下記のように具体的な事項に沿って、緊急事態の対応を決めておくのが一般的です。
・地震や火災が発生した場合の避難経路や避難場所
・事故や災害で混乱が発生した場合の来場者への対応や誘導方法
・不審者が侵入した場合の対応や来場者の誘導方法
・熱中症や食中毒など体調不良の参加者が出た場合の対応
これらの対策をスタッフ全員が共有し、いざという時に適切な対応ができるように、訓練や研修を行うことも必要でしょう。
また、緊急事態が発生した場合は、速やかに責任者や関係機関に連絡を取り、指示を仰ぐ必要があります。そのため、緊急連絡体制を構築して、スタッフ全員が連携できるようにしておくことが、来場者の安全確保につながります。
また、万が一イベントの中止や日程の変更が必要になった場合のことも想定しておくことが大切です。イベントの中止が決まったときは、一般的にメールやSNSなどで中止の連絡をするとともに、払い戻しなどの手続きについて案内を行います。
そう多くあることではありませんが、当日中にイベントの中止が決定した場合は、来場者の混乱や不満の声も大きくなりがちです。そのような場合、混乱が大きくならないように誠実な対応を行い、やむを得ない判断であることを理解してもらう必要があります。その際は、自然災害による安全確保のためなど、具体的な理由を丁寧に説明することを心がけましょう。
いずれの場合であっても、緊急事態が起きた場合は、スタッフ間で共有し、対応に一貫性を持たせることが大切です。参加者の安全を最優先に考え、適切に判断、行動できるように事前準備を行いましょう。
チケットもぎりのやりがいとは
チケットもぎりは一見単純作業に見える業務ですが、さまざまな魅力とやりがいに溢れています。
チケットもぎりは、イベントの入り口でお客様を最初にお迎えする、いわば「イベントの顔」といえる役割です。来場者のイベントに対する第一印象を大きく左右する要素であることから、スムーズな入場誘導や丁寧な対応を行うことにより、イベント全体の成功に貢献しているといえます。
また、お客様と直接接する機会が多い仕事でもあります。来場者の笑顔や「楽しかった」「ありがとう」などの言葉から、イベントの成功を実感できるでしょう。来場者が困ったときには助けになることで、より大きな喜びが感じられます。
さらに、会場の一体感や臨場感を楽しめることも醍醐味の1つです。もぎりスタッフもイベントを構成する一員として、来場者と一緒に空間を作り上げています。
もぎりスタッフは、イベントの準備段階から関わる場合もあります。会場設営の様子やスタッフの動きなど、普段見ることができないイベントの裏側を知る機会になるかもしれません。イベントがどのように作られるのかを知ることで、より深く楽しむことができるでしょう。
チケットもぎりは大きく目立つことの少ない業務ですが、短期間で多くの経験を積める仕事です。自分の仕事がイベントの成功につながっている実感は、大きな達成感とやりがいを与えてくれます。これらの経験は、将来の進路選択や就職活動にも役立つかもしれません。
チケットもぎり業務の口コミ

実際にチケットもぎり業務に取り組んだ人からは、下記のような口コミがあがっています。
”お客さんに「楽しんでください!」と声をかけたら、笑顔で「ありがとう!」と返してくれて、それが嬉しかった。”
”チケットの半券を記念に取っておく人がいるから、大事にもぎらないといけないところが難しい。いい経験になった”
”チケットもぎりのバイト、いろんな人がきて面白かったなあ。イベント開始後は暇だったけど、またやってみたい”
”チケットもぎりのバイトをしていたとき、「ありがとう」って言ってくれるお客さんは、本当に素敵に思えたし、嬉しかった”
”立ち仕事で足が疲れたけど、イベントが始まる前のワクワク感を共有できて楽しかった。コミュニケーション能力も上がったかもしれない”
チケットもぎり業務の口コミには、難しさを感じる半面、楽しさややりがいに溢れるといった意見が多く見られました。イベントを支える一員として、達成感を得られる仕事といえるでしょう。
まとめ
チケットもぎりは、イベントの成功に不可欠な存在です。その業務内容は多岐に渡り、高い意識と責任感を持って業務に取り組むことが求められます。
チケットもぎり業務をスムーズに行うには、電子チケットの導入もおすすめです。導入を検討される際は、複数のシステムを比較検討し、無料トライアルやデモなどを活用して実際に操作してみることをおすすめします。
「CLOUD PASS」は、チケット販売プロセスを簡素化し、販売機会の最大化を支援するチケット販売システムです。チケットの発行や販売、管理を一元化でき、人手や時間のコストを削減できます。イベントの運営を効率化し、収益向上につなげたい方はぜひお試しください。