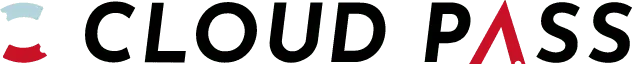クラパス活用術
オフィスセキュリティ対策のポイントは?具体例もまとめて紹介
更新日:
投稿日:
近年、企業の情報資産や従業員の安全を守るため、オフィスのセキュリティ対策がますます重要視されています。不正侵入や情報漏えいを防ぐには、物理的・情報的な対策を総合的に講じなければいけません。
この記事では、オフィスセキュリティの基本から、具体的な対策のポイント、ゾーニングの考え方、実際に導入されている設備やツールの事例までを詳しく解説します。セキュリティ体制の見直しや強化を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
オフィスセキュリティとは

オフィスセキュリティとは、企業の大切な情報や資産、そして働く社員の安全を守るために行うさまざまな対策のことです。大きく分けると、空間を守る「空間セキュリティ」と、情報を守る「情報セキュリティ」の2つに分類されます。
空間セキュリティは、防犯カメラや入退室の管理など、オフィスに出入りする人や物の動きに関わる物理的な安全対策です。一方、情報セキュリティはシステムへのアクセス制限やデータの暗号化など、企業が保有する情報を外部からの攻撃や内部不正から守るデジタル的な管理手法です。
オフィスの物理的な安全はもちろん、近年はサイバー攻撃も高度化していることから、両方の対策をバランスよく整えなければいけないのです。
オフィスセキュリティが重要な理由
オフィスには日々多くの情報や人、資産が行き交っており、ひとたびトラブルが起きれば企業にとって大きな損害を招く可能性があります。そのため、セキュリティ対策は単なる設備の導入ではなく、企業活動を安定的に続けるために不可欠な取り組みと言えるでしょう。
ここでは、オフィスセキュリティが重視される主な理由について詳しく解説します。
情報漏えいを防ぐため
企業が保有する顧客情報や営業データ、契約書類、技術資料といった情報は、いわば会社の財産とも言える存在です。こうした重要な情報が外部に流出すれば、取引先や顧客からの信用を失い、契約破棄や損害賠償といった深刻な事態を招く恐れがあります。
近年は個人情報保護法や各種のサイバーセキュリティ法令も整備されており、万が一情報漏えいが発生すれば法的な責任を問われるケースも。こうしたリスクを回避するために、物理的・技術的な両面からのセキュリティ対策が求められているのです。
従業員を守るため
社員が安心して働ける環境を整えることは、企業にとって大きな責任です。オフィスセキュリティが不十分なままでは、誰でも自由に社内へ立ち入りでき、不審者による盗難や暴力などのリスクを招くことになります。
たとえ直接的な危害を加える意図がなかったとしても、侵入者が逃走中に従業員に怪我を負わせるといったケースも考えられるでしょう。入退室の管理や監視カメラの設置など空間的なセキュリティ対策を講じることで、従業員の安全を確保し、安心して業務に集中できる職場環境が整えられます。
オフィスにある資産を守るため
オフィスには、パソコンやサーバー、金庫、重要書類など、価値のある資産が数多く存在します。外部からの侵入によって資産が盗まれたり破壊されれば、企業にとって大きな損失となり、事業継続に影響しかねません。
セキュリティ対策により、資産を守ると同時に企業としての信頼性を高めることにもつながります。物理的な対策に加え、アクセス制限や機器管理などを通じ、資産の保護体制を万全に整えましょう。
オフィスセキュリティ対策のポイント

オフィスセキュリティを強化するには、やみくもに設備を導入するのではなく、自社の状況に合った対策を段階的に進めましょう。
まずは保有している情報資産の全体像を正確に把握し、管理上の課題を明確にすることが第一歩となります。その上で、必要なシステムやツールを導入し、適切な運用ルールを設け、物理的な空間設計にも配慮します。
ここでは、オフィスセキュリティを整備する上で、意識すべき主なポイントを見ていきましょう。
情報資産の把握
最初にすべきは、自社が保有している情報資産の洗い出しです。顧客情報や財務データ、開発情報などの無形資産に加え、紙の資料、パソコン、USBメモリ、クラウドストレージといった有形の媒体も含めて確認します。
また、それらの情報を誰が使用しているのか、どこに保管されているのか、責任者は誰なのかといった運用実態も含め整理してください。情報の所在と活用状況を可視化することで、リスクの所在や管理上の抜け漏れが明確になります。
課題と必要な対策の確認
情報資産を把握したら、それぞれの管理状況に対するリスクを洗い出し、対応すべき課題を明確にします。
例えば、重要なデータに誰でもアクセスできる状態であれば、誤送信や漏洩のリスクが高まります。また、紙の資料が施錠されていないキャビネットに放置されていれば、持ち出しの危険性も考えられるでしょう。
これらのリスクに対しては、アクセス制限や保管方法の見直し、閲覧者の制限など、具体的な対応策によりセキュリティが強化されます。
セキュリティシステムやツールの導入
課題が明らかになったら、それを解決するためのシステムやツールを検討します。入退室管理システム、防犯カメラ、ICカード認証、ファイアウォールなど、目的に応じた対策が可能です。
ただし、システムは導入すること自体が目的ではなく、リスクへの対応手段であるため、必要性や費用対効果をよく吟味してください。あらかじめ導入目的を明確にし、自社にとって最も効果的な方法を選びましょう。
関連記事:セキュリティゲートの価格相場&メリット・デメリットについて
セキュリティシステムの運用ルールの決定
導入したシステムやツールを効果的に活用するには、日常の運用ルールを明確にしておきましょう。誰がどのように操作・確認するのか、トラブル時の対応フローをどうするかなど、具体的な運用方針を定めておくと良いです。
併せて、社員全体にセキュリティ意識を浸透させるため、マニュアルの整備や定期的な研修の実施も必須。こうしたルールや教育の徹底が、人的ミスによる情報漏洩を未然に防ぎます。
ゾーニングの検討
オフィスのレイアウトもセキュリティ対策に直結します。エントランスや応接スペースといった外部の人が立ち入る場所と、社内の機密性が高いスペースを明確に分け、セキュリティレベルに応じてゾーニングすると良いでしょう。
一例として、サーバールームや機密書類の保管場所は、業務動線の奥まった場所に配置し、アクセス制限を設けることで安全性を高められます。効率的な業務運営とセキュリティの両立を図るためにも、ゾーニングは欠かせない視点です。
オフィスセキュリティ対策におけるゾーニングのポイント

オフィスセキュリティを高める上で、ゾーニングの設計は重要な役割を果たすと解説しました。ただ空間を区切るだけではなく、どこに誰が立ち入り、どのような機能を担うスペースが必要かを明確にすれば、業務効率とセキュリティの両立が可能です。
ゾーニングを適切にすることで、外部からの不正侵入や情報漏洩のリスクを抑えながら、従業員が快適に働ける環境を整えられるのです。ここでは、ゾーニングする際に意識すべき3つの観点について解説します。
用途別スペースをリストアップする
まず最初に取り組むべきは、オフィス内でどのような用途のスペースが必要かを洗い出す作業です。
来客対応を重視する場合は受付ロビーや応接室、機密性の高い業務を行うなら専用の会議室、書庫などが必要です。それぞれのエリアが果たす役割と、セキュリティ上の重要性を明確にすることで、空間設計にブレが生まれにくくなります。
また、情報資産や機器の保管場所も、この段階でリストアップしておきましょう。必要なスペースの整理と優先順位付けが、的確なゾーニングの第一歩となります。
動線を確認する
次に確認すべきは、社内外の人々がどのようにオフィス内を移動するか「動線」の確認です。取引先や宅配業者などの訪問者が通るルートは、できる限り社員の執務スペースや機密エリアと交わらないように設計すべきです。
そうすることで、セキュリティの確保と業務効率の向上を両立できます。また、来客対応を担う部署や社員にとっても、分かりやすくスムーズな動線があることで対応時の負担を軽減できます。
動線の設計においては、通路を確保するだけでなく「誰が、いつ、どこを通るのか」といった運用面まで見据えて検討しましょう。
各ゾーンに適したセキュリティを設定する
ゾーニングが完了したら、それぞれのエリアに応じたセキュリティレベルを設定しましょう。以下の表はレベル分けの一例です。
| セキュリティレベル | 管理内容と主な対策例 |
| レベル1(来訪者向けの一般スペース) | オフィス入り口や受付エリアなど外部の人が立ち入る場所。監視カメラの設置や受付スタッフによる目視チェックなど、基本的な監視体制が中心。 |
| レベル2(応接・共用スペース) | 来客と社員が接する打ち合わせスペースなど。入退室履歴を残す仕組みや、パーティションによる視線・音の遮断が効果的。 |
| レベル3(社員中心の執務エリア) | 社員が日常的に使用するワークスペース。ICカードによる入室制限や個人ロッカーの設置により、内部の情報保護を強化。 |
| レベル4(管理職・機密エリア) | 役員フロアや資料保管室など、限られた社員のみが利用するエリア。複数の認証ステップや監視強化が求められる。 |
| レベル5(極秘データ・設備エリア) | サーバールームや重要文書の保管庫など、社内で最も厳重な管理が必要な場所。指紋認証や暗証ロック、二重扉など多層的なセキュリティで保護。 |
このように、それぞれのスペースの用途や重要度に応じて、セキュリティレベルを段階的に分けて設計するのがポイント。また、導入する設備が過剰にならないよう、コストのバランスを考慮しましょう。
オフィスセキュリティ対策の具体例

オフィスの安全性を高めるために、状況や目的に応じてセキュリティ機器、システムを導入しましょう。ここでは、実際に多くの企業で採用されている代表的なセキュリティ対策について、それぞれの特徴や効果を紹介します。
物理的な侵入防止対策から、情報へのアクセス管理まで、用途に応じた対策を検討しましょう。
防犯カメラ
防犯カメラは、セキュリティ対策の中でも特に導入されやすい設備です。カメラを設置することで「見られている」という意識が働き、不審者の侵入や内部不正の抑止につながります。
設置場所としては、エントランスやエレベーターのような人の出入りが多い場所のほか、資料室やサーバールームといった重要エリアへの設置も効果的。映像記録によってトラブル時の証拠が残る点も、防犯カメラの大きな強みでしょう。
入退室管理システム
入退室管理システムは、オフィス内の立ち入りを制限し、誰がいつどこに出入りしたかを記録・管理するためのシステムです。特定のエリアに入れる人物を制限できるため、社外の来訪者や一部社員のアクセス範囲を制御することで、情報漏えいや物品の紛失を防止できます。
また、職位や部署によってアクセス権限を分ける運用も可能で、管理性とセキュリティの両立が図れます。多様な認証方式を選べるのも入退室管理システムの魅力でしょう。
関連記事:入退室管理システムの特徴・メリットと導入時に確認したいポイント
テンキー認証
テンキー認証は、事前に設定された暗証番号を入力することでドアのロックを解除するシンプルな認証方式です。比較的低コストで導入できるため、小規模なオフィスや一部エリアの制限に向いています。
操作も直感的で、社員が頻繁に出入りする場所に便利です。しかし、暗証番号が他人に知られてしまうリスクもあるため、番号の管理や定期的な変更といったルールの整備が重要になります。
ICカード認証
ICカード認証は、社員証などに埋め込まれたICチップをリーダーにかざすことで入退室を制御する方法です。個人ごとにアクセスログを残せるため、不正アクセスの追跡がしやすく、セキュリティ管理のレベルを高められます。
また、カードの複製が難しい点も安心材料となりますが、カードの紛失や貸し借りによるリスクもあるため、運用上のルール作りと合わせて導入を進めましょう。
スマートフォン認証
スマートフォン認証は、専用アプリを使って入退室を制御する方法。ICカードの代替として近年注目を集めています。
スマートフォンさえあれば新たな物理キーの配布が不要で、導入コストや管理の手間を抑えられます。アプリにはアクセス権限の変更や遠隔操作機能なども搭載されており、柔軟な運用が可能です。
カードのように紛失するリスクも低く、デバイスの扱いに慣れた企業であれば、導入しやすい選択肢となるでしょう。
生体認証
生体認証は、指紋や顔、静脈、虹彩など、人間の身体的な特徴を利用した認証方式です。なりすましや偽造が極めて難しく、高度なセキュリティが必要とされるエリアでの利用に適しています。
サーバールームや機密資料の保管室、または役員専用エリアなどで採用されるケースが増えており、より確実な本人確認が求められる場合におすすめ。近年では、生体データの登録が短時間で完了できる機器も多く、運用のハードルも下がりつつあります。
金庫や鍵つきの書庫
重要な機密文書や情報資産を守るためには、しっかりと施錠管理ができる収納設備が必要です。紙資料の保管には、鍵付きのキャビネットや金庫を利用し、関係者以外の手が届かないようにしましょう。
ICカードや指紋認証を用いた電子錠タイプの金庫も普及しており、物理的な鍵管理の手間を軽減しつつセキュリティレベルを高められます。金融機関や法務関連の業務を行うオフィスでは、こうした収納の導入が欠かせない対策となっています。
セキュリティに配慮したクリヤーホルダー
オフィス内での一時的な書類の持ち運びや保管には、特殊加工が施されたセキュリティ仕様のクリヤーホルダーを活用することで、のぞき見などの情報漏洩リスクを軽減できます。
例えば、用紙の内容が真正面以外からは判読しにくい素材を使用したホルダーは、外出先での利用や外部の目に触れやすい場所でも安心して使用できます。
見た目は通常のクリヤーホルダーと変わらないため、扱いやすさを保ちつつ情報を守ることができるアイテムです。
シュレッダー
不要になった紙の書類でも、油断してそのまま廃棄してしまえば情報漏洩につながる恐れがあります。個人情報や機密事項が含まれる文書は、確実に内容が読めなくなるよう、シュレッダーにかけてから処分するのが基本です。
特にクロスカットやマイクロカットといった細かく裁断できる機種を使用すれば、復元のリスクも大きく下げられるでしょう。どの書類をシュレッダーにかけるべきか、社内でルールを設けて運用してみてください。
パーティション
パーティションの設置は、オフィス内の視線をコントロールし、プライバシーや情報の保護に効果的です。
来客対応スペースでは目隠し効果を発揮し、不要な情報の露出を防げます。また、社員同士の机を仕切ることで、モニター画面や手元の書類が他人の目に入りにくくなり、業務中の情報漏洩リスクも低減できます。
完全に囲われた間仕切りを設置すれば、個室に近い空間を作れるでしょう。
サウンドマスキング
会議や商談などで取り扱うセンシティブな会話内容は、声が漏れ聞こえてしまうことで思わぬ情報漏洩の原因になります。こうしたリスクを軽減する手段として、サウンドマスキングという技術が注目されています。
エアコンの風音のような一定の雑音を意図的に空間に流し、周囲の会話を聞き取りづらくする方法です。完全な防音工事をしなくても、オフィス全体の音のプライバシー性を高める効果があり、特に会議室や集中ブースのエリアに適した対策です。
セキュリティゲート
オフィスのエントランスは、不審者の侵入を防ぐだけでなく、社員や関係者の入退場を正確に管理する重要なポイントです。こうしたアクセス管理を強化する手段として、セキュリティゲートの導入が進んでいます。
QRコードやICカード、生体認証などの識別情報をもとに通行を制御することで、許可された人物だけが通過できる仕組みを構築できます。また、入退場の履歴をクラウド上で管理することで、セキュリティだけでなく労務管理や施設利用の最適化にもつながります。
関連記事:【2025年最新】QRコード受付システム・アプリおすすめ10選!失敗しない選び方も解説
オフィスのセキュリティ対策は用途で使い分けよう

オフィスセキュリティは、情報漏えいや不正侵入のリスクを防ぎ、社員や企業資産を守るうえで欠かせない取り組みです。空間・情報の両面から対策を講じることで、トラブルの未然防止と業務環境の向上が期待できます。
本記事を参考に、自社に合ったセキュリティ体制の構築を進めていきましょう。