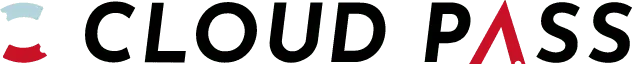クラパス活用術
美術館におけるDXとは?メリットや導入事例も紹介
更新日:
投稿日:
近年、美術館業界でもDX(デジタルトランスフォーメーション)の波が押し寄せています。
DXは単なるデジタル化ではなく、デジタル技術を活用して業務プロセスや来館者体験を根本から変革する取り組みです。人手不足や業務効率化といった課題解決だけでなく、新たな鑑賞体験の創出や来館者データの活用など、美術館の可能性を大きく広げる力を持っています。
本記事では、美術館におけるDXの意義やメリット、具体的な導入事例を紹介します。また、DXを進めるうえでの重要なポイントも解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
DXとは?

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して、組織やビジネスの在り方を根本から変革することを指します。単なる業務の効率化だけでなく、新しい価値を生み出し、組織文化も含めた全体的な変革を実現することが特徴です。
従来のIT化は「既存の業務をデジタル化して効率を上げる」ことを目的としています。一方、DXは「デジタル技術によって何が実現できるか」という視点で、ビジネスモデルの変革や新しいサービスの創出を目指すものです。
近年では、AI・IoT・ビッグデータなどの最新技術を活用し、お客様により良い体験を提供することで、企業の競争力を高める手段として注目されています。
美術館におけるDXのメリット

美術館でDXを推進することで、運営面から来館者サービスまでさまざまなメリットを得られます。ここでは、以下5つのメリットを解説します。
・人手不足を解消できる
・作業効率が向上する
・業務の幅が広がる
・様々なデータが分析できる
・リピーターを増やせる
それぞれ見ていきます。
人手不足を解消できる
美術館運営において、チケット販売や入館管理・案内業務など、人手を要する業務は数多く存在します。しかし、DXの導入により多くを自動化できます。
たとえば、チケットのオンライン予約システムやデジタルチケットの導入により、窓口での対応時間を大幅に削減。また、館内案内をデジタルサイネージやスマホアプリに任せることで、スタッフの案内業務の負担も軽減できます。
とくに混雑時期には、限られたスタッフでも効率的な運営が可能になります。
作業効率が向上する
美術館には作品管理や展示計画の立案、来場者数の集計などさまざまな管理業務が存在します。DXの導入により、これらの業務を一元管理することが可能です。
たとえば作品データベースのデジタル化により、作品の保管状況や展示履歴を効率的に確認できます。また、売上データや来場者データを自動集計し、レポート作成にかかる時間も短縮するでしょう。
さらに、展示スケジュールの管理や作品の貸出管理もシステム化することで、業務の正確性が向上し、ヒューマンエラーのリスクも低減します。
業務の幅が広がる
DXの導入により、従来の美術館運営の枠を超えた新しいサービスの提供が可能です。たとえば、オンライン展示やバーチャルツアーの実施により、物理的な展示スペースの制限を超えた展示が実現します。
また、SNSを活用した情報発信やデジタルアーカイブの公開により、より多くの人々に芸術作品を届けられます。さらに、オンラインワークショップや講座の開催など、来館者との新しい交流の機会を創出することも可能です。
作品解説のデジタル化により多言語対応も容易になり、海外からの来館者へのサービス向上にもつながります。
さまざまなデータを分析できる
美術館の運営において、来館者の行動や興味を把握することは重要です。DXの導入により、たとえば入場者数の推移や滞在時間、人気のある展示作品・混雑状況などをリアルタイムで把握できます。また、チケット販売データからは、年齢層や居住地域といった来館者の属性も明らかになってきます。
これらのデータ分析は、展示内容の改善や効果的な広報戦略の立案に大きく貢献するでしょう。さらに、アプリやWebサイトの利用状況から、オンラインでの情報発信の効果測定も可能です。
リピーターを増やせる
美術館の持続的な運営には、定期的に来館してくれるリピーターの存在が欠かせません。DXを活用することで、来館者1人ひとりに合わせたサービス提供が実現します。
たとえば、デジタル会員証の導入により、来館履歴や興味のある分野を把握し、それぞれの嗜好に合わせた展示情報をメールやアプリで届けることが可能です。
また、オンラインでの展示解説や関連コンテンツの提供は、来館前後でも美術館との接点を維持することにつながります。さらに、予約システムの導入による混雑緩和は、快適な鑑賞環境の実現に寄与します。
美術館のDXの事例

美術館におけるDXの取り組みは、来館者体験の向上や運営効率化、新たな価値創造など多岐にわたります。以下に、いくつかの具体的な事例を紹介します。
・予約システムの導入
・SNSの活用
・デジタルコンテンツの作成
・オンライン対話鑑賞の実施
詳しく解説します。
予約システムの導入
美術館の入館受付において、オンライン予約システムの導入が進んでいます。予約から決済、顧客管理・集客までを一元化することで、業務効率の大幅な向上を実現。
とくに人気の企画展では、時間指定制の予約システムにより来館者の分散化に成功しています。QRコードを活用した入場確認により、当日の受付もスムーズに。
また、音声ガイドや車いすなどの備品予約機能も統合されており、リソース管理の効率化にも貢献しています。事前決済の導入により、窓口での会計業務も大幅に軽減され、スタッフの負担軽減と来館者の満足度向上を同時に達成しています。
SNSの活用
美術館におけるSNS活用は、単なる情報発信ツールから戦略的な集客手段へと進化しています。InstagramやXを通じて、展示作品の見どころや館内の様子をタイムリーに発信することで、新たな来館者層の開拓に成功。とくに若い世代への訴求効果が高く、美術館の敷居を下げる役割も果たしています。
埼玉県立近代美術館では、Facebookなどを活用して県内外のアーティストや市民、支援者をつなぐプラットフォームを構築。美術館の存在価値を効果的にアピールし、アート関連のアウトリーチ・プログラムの展開にもつながっています。
デジタルコンテンツの作成
美術館の所蔵品や展示空間のデジタル化が急速に進んでいます。高精細画像によるデジタルアーカイブの構築や、VR技術を活用した展示室の再現など、時間や場所を問わない鑑賞環境を実現します。
世田谷美術館では、オンライン講座やイベント、展示作品の映像紹介・ポッドキャストなど、多様なデジタルコンテンツを展開。特別な知識がなくても美術を楽しめる仕組みを構築し、新規来館者の獲得に成功しています。また、学芸員による作品解説動画の配信など、美術館の専門性を生かしたコンテンツ制作も進んでいます。
オンライン対話鑑賞の実施
コロナ禍を機に、美術館での新しい取り組みとしてオンライン対話鑑賞が注目を集めています。国立美術館では、Zoomを使用した少人数制の鑑賞プログラムを展開。ガイドスタッフと参加者が対話しながら作品を深く理解していく、これまでにない鑑賞体験を提供しています。
特筆すべきは、広報担当者と学芸員の協力体制です。専門的な知識と分かりやすい解説を組み合わせることで、美術館の魅力を効果的に伝えることが可能となりました。さらに、この取り組みは遠隔地の学校への教育プログラムとしても活用され、美術館の新たな可能性を切り開いています。
美術館におけるDXの進め方
DXの導入は、単にデジタル技術を取り入れることではありません。美術館の運営をより良いものにするための手段として、計画的に進めていく必要があります。ここでは、効果的なDX推進のための4つのステップを解説します。
・目標を明確にする
・現状を分析する
・企画、立案する
・PDCAサイクルを回す
詳しく見ていきます。
目標を明確にする
DXを推進する際、もっとも重要なのは目的を明確にすることです。デジタル技術を導入するだけでは、真の変革は実現できません。まず、美術館が抱える課題は何か、DXによって何を実現したいのかを具体的に定めましょう。
たとえば、来館者サービスの向上や業務効率の改善、新しい芸術体験の創出など、具体的な目標を設定します。この際、現場スタッフの意見を積極的に取り入れることが大切です。トップの意思を明確にしながらも、現場の理解と協力を得られる目標設定を心がけましょう。
現状を分析する
DXを効果的に進めるためには、美術館の現状を正確に把握することが不可欠です。まず、業務の棚卸しを行い、既存のシステムと業務の関係性を整理します。どの業務に時間がかかっているのか、どこにミスが発生しやすいのか、スタッフの負担が大きい作業は何かなど、具体的な課題を洗い出します。
また、来館者アンケートやスタッフへのヒアリングを通じて、サービス面での改善点も明確にしましょう。この分析結果が、効果的なDX施策の立案につながります。
企画・立案する
現状分析で明らかになった課題に対して、具体的な解決策を検討します。この際、すべての課題を一度に解決しようとするのではなく、優先順位をつけて段階的に進めることが重要です。
導入するシステムの選定や必要な予算の見積もり、実施スケジュールの作成など、実行計画を具体化します。また、社内の推進体制も整備しましょう。必要に応じて外部専門家の支援を受けることも検討し、確実な実行につなげます。
PDCAサイクルを回す
DXの取り組みは、導入して終わりではありません。導入後の効果を測定し、継続的な改善を行うことが肝要です。KPIの達成状況を確認し、想定どおりの効果が得られているか評価します。
また、スタッフや来館者の声を集め、新たな課題や改善点を見つけ出します。必要に応じて計画を見直し、より効果的な施策を検討していきましょう。地道にPDCAサイクルを回し続けることが、DX成功の鍵となります。
美術館のDXを簡単に行う方法
美術館のDXは、一度にすべてのシステムを導入する必要はありません。まずは、来館者との重要な接点であるチケット販売のデジタル化 から始めるのがおすすめです。クラウドパス のようなチケット販売・管理システムを活用すれば、予約、入場管理、データ分析 まで一元化でき、業務の効率化と来館者の利便性向上を両立できます。
【美術館向けの主な機能】
・オリジナルチケットデザイン:美術館のブランドや展示に合わせたデザインが可能
・展示ごとの設定変更:特別展や企画展ごとにチケット販売条件をカスタマイズ可能
・日時別の人数変更:混雑状況に応じた入場管理が可能
・ハードウェア連携:ゲートシステムや館内機器との連携でスムーズな運用を実現
・入退場受付の省人化、無人化:スタッフの負担を軽減し、業務の効率化を推進
・セット券の販売:館内のショップやカフェで利用できるチケットや、特定の展示とセットになったチケットの販売が可能
さらに、クラウドパスなら複数施設の一括管理や売上データの自動集計 も可能。戦略的な運営計画の立案にも役立ちます。
設定から販売サイトの作成まで専門スタッフが365日体制でサポート するため、スムーズなデジタル化が可能。運用開始後も継続的なサポートを受けながら、DXを着実に進められます。
まとめ
美術館におけるDXは、業務の効率化や来館者体験の向上、新たな収益モデルの創出など多方面での可能性を広げる重要な取り組みです。具体的な目標設定や現状分析を行い、適切なツールを活用することで、DXはより効果的に推進できます。
とくに「クラウドパス」のようなサービスを導入すれば、運営効率を高めつつ来館者満足度を向上させることが可能です。これからの美術館運営において、DXは欠かせない要素となるでしょう。