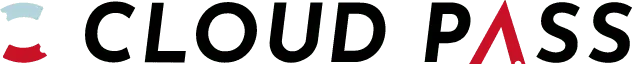クラパス活用術
入退室管理システムの特徴・メリットと導入時に確認したいポイント
更新日:
投稿日:
入退室管理システムは、建物やイベントの入場口、セキュリティレベルの高い部屋などに導入されているシステムです。
物理的な鍵を必要としないため、入退室のために何度も鍵を開け閉めする必要がなく、入退室者にかかわる労務管理や勤怠管理の効率化を実現します。セキュリティ面を強化するうえでも有効です。
物理的な鍵はセキュリティ上の問題が多く、不法侵入などのリスクや鍵の管理に課題がありました。そこで、さまざまな認証方法に対応し、課題解決に役立つ入退室管理システムのメリットや価格帯、比較ポイントについてわかりやすく紹介します。
この記事では、入退室管理システムの特徴とタイプを紹介します。システムの選び方や価格相場についても解説していますので、製品選定の参考にしてください。
目次
入退室管理システムとは

入退室管理システムは、部屋や建物への入室・退室を行い、その記録を保持するシステムです。
入退室を実施した日時・氏名・部屋や建物の場所を記録管理するもので、情報はすべてクラウドなどに保存され、一括で管理されます。
入退室システムが登場する前は入退室のために物理的な鍵や電子錠でロックをかけていましたが、物理的な鍵は紛失リスクが高く、鍵をかけるだけではいつ誰が入退室を行ったかが記録できないデメリットがありました。
入退室管理システムは、ICカードや生体認証といった個人を特定できる情報を利用し、ロックの解除や入退室管理を実施する仕組みです。
社員やスタッフのみに入室・退室の権限を設けたり、業者など一時的に入退室の必要がある場合は日時を決めて権限を与えたりする方法も可能です。
入退室管理システムは、従来の物理鍵や電子錠をそのまま利用できるシステムです。物理鍵は工事を行わずに取り付けられるものもありますが、自動ドアや電子錠は認証リーダーや基板の設置が必要になるため、鍵やドアの種類に合わせてシステムを選ぶ必要があります。
鍵やドアごと入退室管理システムに合わせて交換する方法は変更点が多くコストがかかりますが、システムと連動する専用の鍵に切り替えることで、反応スピードの速さやセキュリティレベルの高さがメリットです。
自動ドアや電子錠だけでは「共連れ」と呼ばれる行為をシャットアウトできないため、入退室の権限をもたない第三者による不正侵入のリスクがありました。そのため、一人ずつの入退室に制限したり、未認証者を検知してアラートを鳴らしたりする共連れ防止機能を搭載した入退室システムが注目されています。
入退室管理システムを導入するメリット

入退室管理システムを導入することで、セキュリティの強化や勤怠管理の効率化、入退室状況の把握が行えるようになります。メリットを詳しく確認していきましょう。
メリット①セキュリティを強化できる
入退室管理システムは、物理的な鍵を使う必要がなくなるため、鍵の管理を必要としません。物理的な鍵は紛失や盗難、不正に複製されるリスクがありますが、入退室管理システムを搭載すればそれらの心配はありません。
さらに、特定エリアへのアクセス権限を明確化します。第三者の不正侵入や共連れの防止、許可されていない人が誤って立ち入ってしまうトラブルなどを防止することができます。
システムによっては、権限を付与された個人を特定する方法として生体認証や多要素認証を利用できます。指紋・顔認証・PINコード・暗証番号など複数の要素を組み合わせて認証します。
メリット②関係者の入退室状況を把握できる
入退室管理システムは、権限が付与された人物の入退室状況を正確に把握できるシステムです。
生体認証やIDカードなどによる個人の特定とあわせてリアルタイムで記録を行い、データはすべてログとして保存されます。過去のログを分析し、不審な行動を特定してセキュリティ対策を強化するといった方法にも応用できます。
特定の時間に限定して入退室者のログを分析すれば、その時間帯に誰が何回どこに出入りしたかをチェックできます。不審な行動の検知によって、権限が付与されていない人が出入りしていないかをすばやく確認できるのです。
関係する社員やスタッフ、外部の関係者など全体の動向を把握できるため、セキュリティ対策にも役立てられます。
関連記事:オフィスセキュリティ対策のポイントは?具体例もまとめて紹介
メリット③勤怠管理・労務管理を効率化できる
入退室管理システムは、出勤・退勤の記録としても利用できます。特定の社員がシステムを利用して入退室を行った場合、その時間が自動的に記録されるため、出勤・退勤したことがログとして残ります。
社員自身が打刻をする必要がなく、また代理で打刻をするといった不正行為の防止にも効果的です。
勤務場所への入退室を自動で記録するため、勤務時間の可視化にも役立てられます。早出や残業が発生したときは打刻の時間が通常と変化するので、ログに記録された時刻から勤務時間を可視化し、労働時間を算出します。これにより、過剰な労働時間の発生を防ぐことができます。
入退室管理システムが勤怠管理や労務管理を自動化するため、業務の効率化や省人化、法令遵守・労働時間の適正化に役立てられるでしょう。
メリット④サイバー攻撃に対策できる
入退室管理システムは部屋や建物へのアクセスを管理するもので、サイバー攻撃そのものに対処するシステムではありません。しかし、適切に運用することでサイバーセキュリティを強化します。
一例として、個人情報や重要情報を扱っている場所では、データを持ち去られたり改ざんされたりしないように、適切に保護しなければなりません。悪意ある人物が自由に出入りできないように入退室管理システムを搭載すれば、不正な情報流出やデータ改ざんを防止できます。
ネットワークセキュリティツールと入退室管理システムを組み合わせれば、異常な行動を入退室の履歴から読み取り、サイバー攻撃の可能性を早期に察知して予防するといった使い方もできるでしょう。
入退室管理システムの導入方法
入退室管理システムを導入するときは、鍵の状況によって対応方法が異なります。現状の鍵をそのまま使う場合、電子錠への対応、扉の鍵ごと変更する場合についてみていきましょう。
現状の鍵を利用したい場合
現状の鍵を変更せずに入退室管理システムを搭載する場合、扉のサムターンなどに専用のデバイスを貼り付けて使います。
デバイスにはカードリーダーなどが搭載され、上からICカードやスマートフォンをかざすとサムターンが回って解錠する仕組みです。
取り付け工事が不要で、既存の鍵を変更せず貼り付けるだけで簡単に入退室が行えます。工事ができない(原状回復が求められる)オフィスなどに適した方法です。
工事が必要なケースでは、鍵のほかに扉を変更しなければならない場合もあり、初期費用がかかります。一方、貼り付けて使うデバイスには大掛かりな工事の必要はありません。
デバイスは簡単に取り外しができるため、オフィスを移転するケースにも適しています。
電子錠に対応させたい場合
電子錠や自動ドアに対応させる方法としては、専用の配線工事が必要になります。電気工事士による工事作業が必要になるため、施工可能な電子錠や自動ドアかどうかを確認しましょう(施工不可の場合は工事不要のシステムを選んでください)。
入退室管理システムが電子錠や自動ドアに対応していることも事前に確認が必要です。施工業者に連絡し、電子錠や自動ドアの横にカードリーダーなどを設置します。基板を電気錠などの制御盤内にも設置します。配線を繋ぎ、入退室管理システムの動作をチェックします。
扉の鍵ごと変更したい場合
入退室管理システムを導入するために扉の鍵ごと交換する場合は、既存の鍵を取り外して新しい鍵に入れ替える必要があります。複数の部屋や建物、拠点がある場合はすべての場所の鍵を入れ替えます。
注意点として、ドアが新しい鍵に適合していない場合は、ドアも交換しなければなりません。こちらも複数の部屋・建物・拠点のドアが新しい鍵に適合していることを確認しましょう。
入退室管理システムの認証方法
入退室管理システムの認証方法には、ICカード・スマートフォンアプリ・暗証番号・生体認証といった方法があります。それぞれの手法を詳しくみていきましょう。
ICカード
ICカードによる認証は、小型の電子チップを埋め込んだ専用のカード(ICカード)を専用のリーダーにかざして読み取らせる方法です。
カード内のチップには、所有者のIDデータが格納されています。所有者自身がカードを持参してIDデータを読み取らせると、システム側とIDデータの照合が行われて認証を完了します。
生体認証と比べて導入コストが低く、ICカードを社員証として扱うこともできるため、柔軟な使い方ができます。暗証番号のように直接入力の手間がかからず、大企業のように多くの人の出入りがある場所にも適しています。
注意点として、ICカード自体を紛失すると第三者による不正利用のおそれがあります。その場合は生体認証やPINコードを組み合わせるといった対策が有効です。
スマートフォンのアプリ
スマートフォンアプリを使った認証は、スマートフォンアプリが発行したQRコードをリーダーに読み取らせたり、スマートフォンがもつNFC機能を使ってリーダーにかざして本人確認をとったりする方法です。
ICカードを持ち歩く必要がなく、手持ちのスマートフォンから直接操作できるため、持ち物を減らし紛失のリスクを防ぎます。スマートフォン自身の生体認証(指紋認証やPINコードなど)が使えるため、本人以外の人に操作されるおそれが少なく、高いセキュリティレベルが確保できます。
企業にとっても、ICカードの新規発行や紛失時の再発行・更新作業にかかる手間・コストを削減できるので、コストダウン効果が期待できるでしょう。
利用状況の確認や管理を遠隔で実施でき、アプリをアップデートして運用を継続できる点が特長ですが、利用者がスマートフォンを紛失した場合はすぐにアカウントを無効化しなければなりません。
関連記事:【2025年最新】QRコード受付システム・アプリおすすめ10選!失敗しない選び方も解説
暗証番号
暗証番号による認証は、入退室時にキーパッドやタッチスクリーンに暗証番号を直接入力する方法です。
ICカードやスマートフォンを使用しないため、スマートフォンが持ち込めないような高いセキュリティレベルが要求される環境に適しています。
暗証番号はすぐに変更できるため、一定の期間使用を続けた番号を新しいものに変更すれば、外部からやってきた第三者に番号を使い回されるリスクを低減できます。
注意点として、利用者が暗証番号を忘れてしまったり第三者に共有したりすると、セキュリティレベルが低下するおそれがあります。利用者自身で正しく暗証番号を覚え、不用意に第三者に漏らすことのないように管理しなければなりません。
生体認証
生体認証とは、利用者の身体的な特徴や行動的特徴を使って個人を特定する方法です。
一例として、指紋・虹彩・静脈・声紋・筆跡といった方法が挙げられます。いずれも第三者が複製しにくいもので、個人を記録する方法としては、IDよりもさらに高いレベルでのセキュリティを発揮します。
生体認証は、利用者ごとに初期登録を行って個人のデータとして管理します。そのデータ以外は認められないため、第三者が認証しようとしても合致しなければ照合失敗となります。
ICカードやスマートフォンを持ち歩く必要がなく、瞬時に認証を行えるため入退室のプロセスがスムーズに行われます。ただし、生体情報は機密性が非常に高いため、データ自身を適切に暗号化して保護しなければなりません。
入退室管理システムを導入する際に確認したいポイント

次に、入退室管理システムを導入する際に確認したいポイントをみていきましょう。
外部・内部両面のセキュリティレベル
外部だけではなく、内部のセキュリティレベルを強化できるかどうかを重視しましょう。ログの分析機能が充実しているか、細かくログや個人の動向をチェックできるかといった点で、複数のシステムを比較します。
機密性の高い情報を扱う環境では、外部の第三者による情報の持ち出しやデータ改ざんといったリスクに対応しなければなりませんが、あわせて内部の対策も強化する必要があります。
一例として、出勤時間外に入退室を繰り返すような不審な行動をとっている人物が確認できれば、権限を外したり詳細な行動を本人から聞き取ったりと、セキュリティ対策を強化できるでしょう。
セキュリティレベルをもっとも高くしなければならない環境には、権限を持たない社員やスタッフが入退室をしないように生体認証を導入するなどの方法を検討しましょう。
関連記事:オフィスセキュリティ対策のポイントは?具体例もまとめて紹介
対応している認証方法
入退室管理では、ICカード・スマートフォン・暗証番号・生体認証とさまざまな方法で認証を行います。初期費用をかけず、スピーディにシステムを設置できるサービスも選べます。
クラウド対応や外部サービスとの連携・連動機能を備えたものも多く、企業の規模や導入場所に合わせた方法が選択できます。
一度に多くの人が出入りする環境では、認証に時間がかからない方法が適しています。暗証番号ではなくICカードのようにかざすだけで通れるもの、あるいは生体認証のように確実性の高い認証方法を採用するといったケースです。
導入コストとのバランスを考え、費用を抑えたいときにはスマートフォン認証も選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。
関連記事:セキュリティゲートの価格相場&メリット・デメリットについて
ほかのシステムとの連携
監視カメラ・労務管理・勤怠管理・カレンダーツールといった外部のサービス・システムと連携できるものは、目的に合わせた使い方を可能にします。システムを選ぶ際、どの程度の連携や連動が行えるのかチェックしてみてください。
防犯性を高めたい環境では、監視カメラと入退室システムを連動させる方法がおすすめです。不審な行動をする個人が確認されると警備スタッフが駆けつけるため、スピーディな対応が可能になります。
カレンダーツールと連動させれば、入退室を行った本人が出勤・退勤日時を確認できるため、勤怠管理に役立てられるでしょう。
外部のシステムやサービスと連携させれば業務がスマート化し、管理者にかかる負担やコストを減らします。入退室を行う利用者にとっても、安心・安全を提供できます。
費用対効果
入退室管理システムにはさまざまな方法があります。生体認証のように高い認証能力を発揮する方法は、導入費用が高額になりやすいため、費用対効果をよく検討したいところです。
費用対効果を検討するためには、初期費用とランニングコスト、その他の費用(カードの再発行や不具合時のメンテナンス費など)に分けて考えます。生体認証のようにハイレベルのセキュリティを確保するシステムは、個人の生体データを安全に保存するための暗号化技術が利用できるかにも注目してください。
支店や営業所のような複数拠点に同じシステムを導入する場合は工事不要か、サーバー不要でクラウド上から操作できるかといった点に注目しましょう。
サポート体制
入退室管理システムは、導入する環境によっては24時間365日のサポートが必要になる場合があります。たとえば、24時間365日人の出入りがある建物では、入退室管理システムも24時間365日稼働させなければなりません。
万が一稼働中に不正な行動やその他のトラブルが発生したとき、スピーディに対処できるように、システムのサポート体制を必ずチェックしてください。
サポートが受けられる場合は、「電話での対応があるか(またはメールやチャットでの対応になるのか)」「訪問サポートが受けられるか」「営業所の場所・対応時間」「メンテナンスにかかる日数」といった詳細部分も確認してみてください。
中小企業向けの入退室管理システム
中小企業向けの入退室管理システムを導入する場合、ニーズや予算に応じた製品選びが重要です。
ニーズについては、セキュリティの強化や業務効率化など具体的な目的を設定すると良いでしょう。
CLOUD PASS(株式会社ユニエイム)

CLOUD PASS(クラウドパス)は、カード型・スマホのQRコードを活用し、幅広い種類のゲートに対応できる受付システムです。ドア解除装置との連携も可能です。
QRコードをかざす完全タッチレスシステムのため、入退室管理・チケット販売・電子錠との連携など幅広いシーンに対応できるワンストップサービスです。
クラウドサービスのためアプリのダウンロードは不要です。API連携・システム開発にも対応しているため、運用状況に合わせたシステムを構築することもできます(具体的な対応状況についてはお問い合わせください)。
ALLIGATE(アリゲイト)

ALLIGATEは、開き戸や自動ドア、ガラス扉などさまざまな扉や既存システムからのリプレイスに対応したクラウド型の入退室管理システムです。
Web管理ツールを使用すれば、ユーザー登録・入退室権限の付与と無効化・複数拠点の管理・入退室ログの閲覧を行うことができます。
スマホアプリやICカードの社員証で解錠でき、FeliCa・MIFAREにも対応しています。オンプレミスシステムでは難しい複数拠点の一元管理、ユーザーの在室管理も可能です。
Web管理ツールを利用した入退室ログ機能を利用すれば、従業員の勤怠管理にも応用できます。
標準機能として、オートロックや共連れ防止のためのアンチパスバック、メール通知や遠隔解錠機能を搭載。非常時への対応として、警備連動機能(最終退館連動)や、火報連動機能も搭載しています。
bitlock PRO(ビットロックプロ)

bitlock PROは、初期費用がかからずに工事不要で貼り付けて使える法人向けのスマートロック・入退室管理システムです。
コストパフォーマンスを重視したシステムで、月額5,000円(税込)からセキュリティを使えるサブスクリプションタイプが特徴。工事不要で取り付けられるサムターンの種類が豊富で、初めての方でも簡単に取り付けられます。
12種類の解錠方法から選べるほか、エリア・時間・所属グループに合わせて柔軟に解錠権限を付与できます。権限のコントロールは管理クラウドシステム上から即時変更できます。
管理クラウドシステムでは、入退室ログの取得・複数拠点の一元管理・解錠放置アラート機能などを搭載。顔認証オプションとの併用によって、設備やシステムへの投資を行わずに顔認証による解錠システムの設置が可能です。
Akerun

Akerunは、後付けで設置できるスマートロックセキュリティシステムです。オフィスのドアに貼り付けるだけで設置できるセキュリティシステムで、初期費用や運用コストを削減しながら、最短で3日の導入かつローコストでスマートロックを導入できます。
認証方法はスマートフォン・社員証・交通系ICカードなどさまざまな方法に対応。出社不要で遠隔鍵管理が行えるため、鍵を管理する負担やコストも低減します。
入退室管理をスマートにするだけではなく、勤怠システムとの連携によって労務を効率化できます。社員やスタッフの業務量を可視化したり、労務管理にかかる負担やコストを軽減したりと、現場の管理業務をスマート化。多拠点の入退室管理の一元化やオフィスの無人化にも貢献するシステムです。
株式会社日立ビルシステムの入退室管理システム

日立ビルシステムの入退室管理システム「BIVALE入退室管理サービス」は、日立カスタマーセンターによる24時間365日のフルサポートが付いたアウトソーシング型入退室管理サービスです。
Nタグシールと呼ばれるカードを社員証などに貼り付けるだけで入退室専用のカードとして使えるようになり、カードリーダーに読み込ませるだけで入退室が行えます。
日立カスタマーセンターは24時間365日遠隔監視を行い、機器の故障に即時対応、オンコールの受付対応やカード使用停止作業の代行、ヘルプデスクとしても機能するサポートサービスです。
各種データの管理はカスタマーセンター側で一括管理し、複数拠点への拡張・管理も可能。クラウド型サービスのためカードの使用権限付与や停止設定、扉の運用時間帯の変更などはインターネット上から実施できます。
大企業向けの入退室管理システム
大企業向けの入退室管理システムは、拡張性や導入・運用コストの面から費用対効果の高いものを選びましょう。
大規模コールセンターなど、多くのスタッフが出入りする場所では、セキュリティレベルに応じた認証方法を選ぶことが大切です。
CLOUD PASS(株式会社ユニエイム)

CLOUD PASSは、美術館やアミューズメントパークのように多くの人が利用する施設にも導入できる拡張性の高いチケット販売・入場管理システムです。
施設やイベントの運用をシンプルかつ効率化するシステムで、入退場・チケットの発券・データ管理などを一元化して管理できます。
カード型やスマートフォンのQRを使った認証方式に対応し、ドア解除装置との連携も可能です。クラウド型のサービスのため、アプリのダウンロードは必須ではありません。
導入にかかる費用やシステム利用料は業界最安値に設定されており、低コストで運用が始められる点も特長のひとつです。
システムの導入〜運用はオンラインマニュアル・オンサイトサポートに加えて、運用代行やメールでの問い合わせに365日対応します。システムのカスタマイズについても事前に相談可能です。
Webvisor

日立システムズのWebvisor(ウェブヴァイザー)は、入退室管理システム・画像監視システムを組み合わせた物理セキュリティソリューションです。
「システム管理者のみICカードと生体認証、一般社員やスタッフはICカード認証を行う」というように、入退室場所やセキュリティレベルに合わせて、認証方式を複数組み合わせた運用が行えます。
画像監視システムとして、IPカメラやハイブリッドDVRを利用した集中管理システムを搭載し、入退室を行った人を常時監視しながら履歴を残します。
基本サービス時間は平日9〜17時ですが、要望によって24時間365日に対応しています。大企業のように入退室者の多い環境に適しており、目的や場所に合わせた物理セキュリティの導入を可能にするソリューションです。
セサモTRⅡ

セコムが提供するセサモTRⅡは、パソコンのブラウザ上から最大で50拠点・400扉までの入退室を一元管理できるトータルセキュリティシステムです。
最大で5万人のユーザーを自動記録するため、勤務状況の把握に貢献。環境に合わせてアンチパスバック機能や入退室時の滞在時間を制限する機能を組み合わせることもできます。
専用端末を使った警戒セット操作のほか、セコムが提供するオンラインセキュリティと連動させて、防犯管理システムへの拡張にも対応。非常時にはセコムのスタッフが駆けつける防犯サービスが利用できます。
認証用のカードはFeliCaなどに対応したマルチカードリーダーが標準で提供され、パソコンを設置していない場所にも遠隔管理ができます。全国に複数拠点を展開する大企業のニーズにも対応できるセキュリティシステムです。
SPLATS

SPLATSはLTE通信昨日を搭載した、ブラウザベースのクラウド型セキュリティサービスです。
ネットワーク工事が不要のため莫大な初期費用がかからず、サブスクリプション方式のためランニングコストも平準化します。
Webブラウザ上から入退室の履歴確認や管理、鍵の使用履歴を確認できるため、管理者にかかる負担を軽減。カレンダーツール・ビジネスチャットツール・予約管理や人事労務システムなどの外部サービスと連携させることで拡張性や利便性を向上させられます。
コントローラーにLTE通信機能を搭載し、利用者はICカードやQRコードを読み取らせて解錠。扉の制御には電気錠制御方式を採用した構成です。
サービスの提供元は全国に営業拠点を展開し、導入前の相談〜設置工事・不具合への対応を細やかにサポート。年中無休のカスタマーセンターとも連携しています。
入室管理システムの特徴や機能を比較しよう

今回は、入退室管理システムの特徴やメリット、認証方法と中小〜大企業に適した製品を紹介しました。
システムには外側から簡単に取り付けられるものから、扉・鍵ごと新しいものに取り替えるものまであります。システムの機能・費用・サポートの有無をよく確認し、自社の職場や出入りする人数に合わせた製品を選びましょう。
検討段階では導入にかかるコストや費用対効果に注目しがちですが、セキュリティレベルに合うかどうか、不具合やトラブル発生時の対応がとれるかといった点も確認し、細かい部分までよく比較する必要があります。
生体認証、監視カメラや防犯サポートと連動した入退室管理システムも選べます。製品ごとの特徴をチェックし、導入を検討してみてはいかがでしょうか。